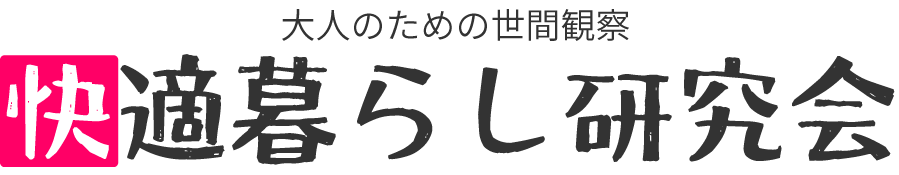トークイベントを行う今村純子さん(中央)、映画喫茶「泪橋ホール」(東京都台東区)
1989~91年にかけての新潟・阿賀野川流域に暮らす人々を描いたドキュメンタリー『阿賀に生きる』(佐藤真監督、1992年)のトークインベントが8月16〜18日、映画喫茶「泪橋ホール」(東京都台東区)で行われていました。
本作品は四大公害病の一つである新潟水俣病(第二水俣病)が起きた阿賀野川を舞台に集落の暮らし、企業城下町ゆえに起きた公害の背景等を映し出しています。
雇用と公害をもたらした大企業は同地域からすでに撤退し、それにともない過疎の進行も見えます。スクリーンに登場する人々の多くは高齢者でした。
傾斜地にある田んぼを守る農夫婦、弟子を取らない頑固者の舟大工、仲の良い夫婦の餅つき職人、いろり端で酒を酌み交わし、茶の間で居眠りをする高齢者たち。近隣の住民たちは宴に集まり、波打つ茶色の畳で雑魚寝をしている……。上映中は、初めて訪れる山村なのに、おじいちゃんやおばあちゃんがいる故郷へ「里帰り」したような懐かしい気分を味わえました。
時折、高齢者の痙攣(けいれん)する指や変形した手の甲の形などが映ると、公害の爪痕が現在進行形であることを暗示させます。しかしながら、映画ではこうした爪痕から世間に対する怨念や恨み、暗さのような意味合いは示されず、むしろ川と共に運命を受け止める明るさを印象付けます。漁や田畑を潤す命の源としての川の存在が描かれていました。
私が会場を訪れた18日、上映後は制作時に住民とスタッフの橋渡し役を担った旗野秀人さんと、美学・哲学の研究者・今村純子さんのトークイベントが続きました。
今村さんは名シーンをいくつか挙げた上で、それでもなお「いろり端や茶の間の出来事だけでは映画として成立し得るだろうか」と作品成立を巡るリスクを問いかけます。これに対し、撮影に携わった旗野さんは「いろり端」や「茶の間」に重点を置く映像が生まれたいきさつを説明しました。
当時の状況は公害を巡る裁判が「日常的」になっていたそうです。こうした社会運動や裁判の風景を「日常」としてメインに捉えると新潟水俣病事件に目を向けられなくなることをスタッフの間では危惧していたと明かしました。こうした危惧がいろり端周辺へカメラを向ける動機となり、結果的に独特の映像美を生み出す方向になったようです。
他に、象徴的な生活音等が本作品で果たす役割や本作品に関連する旗野さんの映像作品を巡っても意見が交わされました。
本作品は悪対正義の単純な対決軸は採用されず、企業城下町ゆえに問題の企業をかばおうとする住民たちの傾向も指摘されており、誰が敵で味方なのかはっきしりしないリアリティは、本作品を鑑賞する上で深みをもたらしていると感じました。